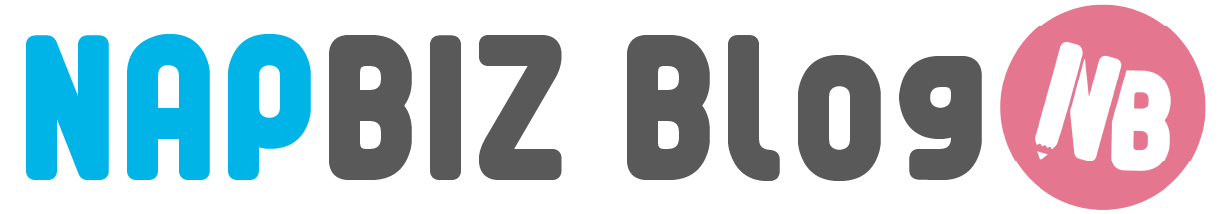チビの愛 第1話
「チビの愛」は昭和が舞台の、母犬の愛情物語です。
私自身の幼少期の思い出をもとに創作しました。

こんにちは。
秋田犬と暮らして23年、2頭の秋田犬を天国に見送り、現在2頭の秋田犬、虎毛の『ぱたこ』と赤毛の『こむぎ』との日々を楽しんでいるぱたこ母です。
今回も最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
【 第1話 】
(新しい家族)
その犬がやって来たのは、夏も終わりに近い九月の初めの事だった。
艶のある焦げ茶の毛並みに、とがった鼻がどことなく気品を漂わせている犬だった。
山の中で生まれたというその犬は、貰い手のないまま一年近くも生家の親元で、たっぷりと甘えて育ってきていた。
兄弟たちは皆貰われて行き、残ったその犬は、母犬と一緒に山中を自由に駆け回って毎日を過ごしていたのだ。
ところが一カ月前、夏の異常な太陽の輝きに負けて、母犬が死んだ。
悪い事は続けて起こるもので、飼い主である主人も病気で入院してしまった。
犬の世話にまで手が回らないと奥さんは言い、隣のおばさんから町へ出た息子へ、その息子からスーパーのおばさんへといった具合で何人ものつてをたどり、その犬はこの小さな工場へと貰われて来たのだった。
その時、工場にはもうすでにゴンという名の体の大きな番犬がいた。
「一匹も二匹も同じだから。」と工場の主人は言った。
けれど、それは犬たちに与えるエサの事でしかなく、家族が残した残飯の量は二匹分くらい充分あるという意味で、首輪もクサリも、ましてや犬小屋などというものはいっさい用意されていなかった。
「欲しくもない犬だから」
と主人はその犬を放し飼いにした。
けれど、その犬は工場を出て行こうとはしなかった。
誰からも歓迎されていないと知りつつも、昼間は埃にまみれて仕事する主人の横に座り込み、静かにその作業を見守った。
そして夜になると、家族の団らんの声が聞こえるリビングの窓の下に体を横たえて眠るのだった。
この工場の他に行く所がない事を、その犬は知っていた。
この町は食べ物の匂いがしなかった。
この町一帯は小さな工場が立ち並ぶすすけた工業地帯で、町へ出ても飲食店は数えるほどしかなかった。
町にはその辺りを縄張りとする野良犬がすでにいるであろう事は簡単に推測できる。
従って、その数少ない飲食店の残飯にありつけるとは到底考えられなかった。
山中で伸び伸びと、母の愛をたっぷりと受けて育ったその犬は、望まれていないと感じつつも、その家に留まった。
別に危害を加えられるわけでもない。
狭いとはいえ、工場の中を自由に走り回る事も出来る。
ただ一つ、山にいた時と大きく違う事は、母犬がいないという事だけだった。
今まで自分と一緒に走り、戯れ、頬ずりしてくれた母がいないという事が、その犬の気持ちを沈ませていた。

けれど、それもほんの数日の事だった。
その犬の大きな身体と精悍な風貌に警戒していたその家の二人の子どもたちは、すぐにその犬を可愛がるようになった。
六歳のアヤは学校から帰って来ると、妹のミチと一緒にその犬を隣の空き地へと連れ出し、「チビ」と呼んで、夏の長い夕暮れを一緒に遊んだ。
首に手を巻き付けて頬ずりするアヤとミチのほっぺは、母犬の温もりに似ていた。
アヤが走る。
その後をミチが走る。
そうして、それをチビが追いかける。
全身が、目が、耳が、そして毛の一本一本までもをアヤとミチに集中させて、風に溶け込んで走るチビは、山の中で母犬と走っているように幸せそうだった。
アヤが止まる。
ミチも止まる。
驚いたチビは前足で急ブレーキをかけ、その反動で体を丸めて草むらへと転がった。
それを見て、アヤとミチはお腹を抱えて笑い転げ、チビの横に寝転んだ。
広い空き地に三人きりだった。
頭の上をバッタやコオロギが跳ねて行く。
もちろん蚊もいっぱい飛んでいる。
「あっ! ミチのほっぺに蚊。」
そう言ってアヤがミチのほっぺをピシャッと叩いた。
「いたーい!」
ミチはほっぺを膨らませた。
「だって、ほら。」
とアヤが差し出した手のひらには、叩いたはずの蚊はいなかった。
「おねえちゃんの嘘つき。」
「嘘じゃないよ! 本当にいたんだから。あっ! ほらっ! 今度はチビの頭に止まった。」
二人の横で静かに座っているチビの頭を指さして、アヤが言った。
「ほんとだ。」
と言うミチの声と同時に、アヤの手がチビの頭に飛んだ。
けれど、子どもの手に蚊が捕まるはずもなく、再び逃げられてしまった。
叩かれたチビはふざけているのだと思い、アヤの体に足を掛け、顔をペロペロなめ始めた。
それを見たミチはおかしさを堪えきれない様子で、
「お姉ちゃんの顔にも蚊が止まってたんじゃないの! ねっ、チビ、仕返しだね!」
とチビに加勢し、後ろからアヤの腰に手を回し、思いっきり引っ張った。
アヤがよろけて倒れ込み、三人で草むらの上をじゃれ合いながら転げ回っていると、遠くでゴンの遠吠えが聞こえた。
ゴンは走る事があまり好きではなく、一緒に遊びに来ても、いつも空き地の隅にある小さな池のがまの穂の陰に隠れて、一人で何やら遊んでいた。
「もうすぐ来るよ!」
アヤがスカートに付いた草を手で払いながら、息をきらせて言った。
ゴンはとても耳が良く、空き地脇の土手の上を走る線路に電車の振動が響き始めると、決まって遠吠えをした。
その声に連られて、チビも鼻を天に向け、
「ワオーン」
と吠えた。
アヤとミチはこの時間が一番好きだった。
そろそろ太陽は西に傾き、犬の遠吠えに送られて電車は真っ赤な空の中を夕日に向かって走って行く。
真っ赤な空には真っ赤な赤とんぼがいっぱい飛んでいる。
すぐ手が届きそうな低い空にいて、アヤもミチも大人になったら手で捕まえられると信じていた。

電車が行くと夜が来る。
家と空き地との境の塀の隙間から、二人の母である奥さんの呼び声がする。
「ご飯よー!」
第2話はこちらからどうぞ
↓↓↓
今では考えられませんが、昔は放し飼いの犬もけっこういました。
かの有名な忠犬ハチ公のお話も、放し飼いだったからこそ成り立つストーリー。
(映画で見ただけなので、実際のところは分かりませんが。)
現代に生きるぱたことこむぎはどこに行くのも私と一緒。
誰を迎えに来たのかもよく分かっていない始末でした(笑)。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
0同じカテゴリの記事
-
前の記事

ぱたこむ劇場(13)飼い主の言いつけに素直に従う可愛い秋田犬こむぎ 2023.07.23
-
次の記事

ぱたこむ劇場(14)膿皮症ケアをして貰う姉の横で悪戦苦闘する秋田犬こむぎ 2023.07.29