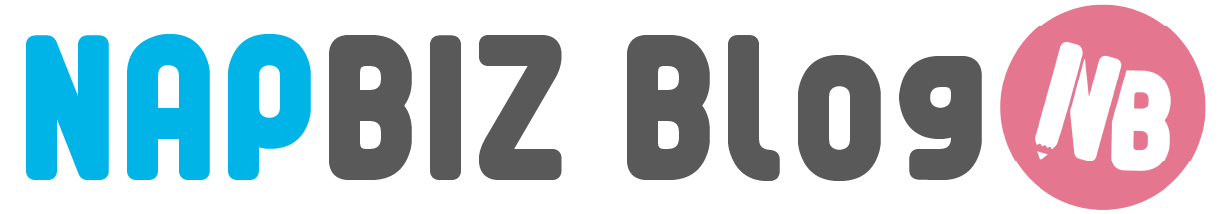チビの愛 第5話(最終話)
「チビの愛」は昭和が舞台の、母犬の愛情物語です。
私自身の幼少期の思い出をもとに創作しました。

こんにちは。
秋田犬と暮らして23年、2頭の秋田犬を天国に見送り、現在2頭の秋田犬、虎毛の『ぱたこ』と赤毛の『こむぎ』との日々を楽しんでいるぱたこ母です。
今回も最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
第4話がまだの方はこちらからどうぞ
↓ ↓ ↓
【 第5話 】
(チビの起こした奇跡)
翌朝、奥さんは暖めたミルクをスポイトの中に入れ、チビの子犬に飲ませようとした。
けれど、子犬は顔を背け、すぐにチビのおっぱいを探して吸い付いてしまった。
昼になっても夜になっても同じ事で、子犬はスポイトのミルクを飲もうとはしなかった。
不思議な事に、何日か経っても、子犬はお腹の空いた素振りを見せなかった。
それどころか、クロの子犬たちに比べて倍くらいの大きさにまでも成長し、そして、チビも日に日に元気を取り戻していった。
驚くべき事に、チビのおっぱいは出るようになっていたのだ。
普通、出産後でなければおっぱいは出ないものなのだが、チビの、そのあくまでも母であり続けたいと願う思いのせいか、それとも子犬を愛する気持ちの深さのせいか、奇跡が起きたのだ。
チビは子犬を立派に育てあげた。
クロの子犬たちが売られて行っても、やはりチビの子犬は真っ黒なため買い手が無く、以前のクロと同じようにチビのもとに留まった。
子犬は肉も魚も食べるようになっていた。
けれど、たった一匹母のおっぱいを一人占めして育って甘えん坊になったせいか、いまだに暇さえあればチビのおっぱいにしがみついていた。
そんな子犬をチビは愛おしみ、こよなく愛した。
エネルギーを持て余している子犬は、時々、寝そべっているチビの背中に飛び乗ったり、手足をかじったりした。
チビがいくら元気になったとはいえ、昔と比べたら衰えている事は歴然としていた。
ほとんど一日中、小屋から一歩出たところで寝そべっており、動くのは用を足しに近くの草むらまで行くのがせいぜいだった。
そして、戻って来た時にはもう息が荒くなっている。
アヤは子犬の乱暴な態度を目にする度に、子犬をチビから引き離した。
チビが自分の身を削って子犬の相手をしているのを見るに耐えなかったからだ。
そんなアヤとはうらはらに、ミチはいつもチビの負担になるような事を子犬にさせた。
寝そべっているチビの背中を飛び越えさせたり、子犬の鼻先をチビの顔に押し付けたりと。

「ミチ、チビは弱ってるんだから、静かにしておいてあげて。」
ある時、見かねてアヤはミチに諭した。
ミチは姉の言葉に、
「でも、こうして遊んでやらないと、子犬はすぐに元気なクロのところに行っちゃうんだよ。
その時のチビの寂しそうな目、お姉ちゃん、見たことある?」
アヤは何も言い返せなかった。
最初から気付き、気付いてない振りを必死でしてきたのに、妹に面と向かって言われてしまった。
黙ってチビの頭を撫でるしか、自分の心の揺れを落ち着かせる方法はなかった。
チビが無理することなく、いつも子犬と一緒にいるにはどうしたら良いのか?
アヤは考えを巡らせた。
その夜、アヤは何故だかなかなか寝付けなかった。
何となく嫌な予感がする。
隣で眠っているミチを揺り起こして二人でそっと外へ出た。
九月の空は澄んでいた。
日中はまだまだ暑いが、夜風は涼しく、肌に気持ち良かった。
月明かりに照らされ犬小屋へと行くと、チビは小屋の前で子犬を包み込むようにして眠っていた。
敏感な子犬はアヤとミチの気配にすぐに気付き、走り寄って来た。
チビも顔を上げ、落ち着いた笑顔で二人を見つめた。

その時、アヤもミチも妙な胸騒ぎを覚えた。
二人を見つめるチビの瞳はいつも通り優しさで溢れ返っていたが、何かがいつもと違った。
何かを訴えるように二人の顔をゆっくりと交互に見つめ、視線を外さない。
アヤはチビのクサリを外すと、チビの顔を両手で包み込んで頬ずりをした。
「今晩からはクロのところへ行って、皆一緒に眠るといいよ。
これからは毎晩そう出来るように、私がクサリを外しに来てあげるからね。」
そう言いながらも、チビにはもうこれからなんてないのかもしれない、と思い、
アヤは勝手に目から溢れて来る涙を止める事が出来なかった。
ミチも、抱いている子犬を下ろしてチビに思いきり抱きついた。
「大好きな子どもたちと一緒に仲良くお眠り。」
二人とも、今日がその日であるような気がしてならなかった。
チビに触れてみて、一層強くそう感じた。
いつにも増して、母の優しさが滲み出ているような気がした。
こんなにやつれても、まだアヤとミチのことを気に掛けていてくれる。
そのことが二人を見つめるチビの瞳の中に色濃く表れていた。
チビはアヤとミチの頬に乾いた鼻先を軽く触れさせると、クロのところまで行き、肌を寄せるようにして横たわった。
子犬もチビにならい、二匹の間に体を埋めた。
三匹はとても静かに寄り添っていた。
三匹とも心底安心しきっているようであった。
アヤもミチも三匹から目を離すことが出来ず、その場に立ち尽くしていたが、
三匹だけの時間に自分たちの存在は必要ないと既に承知していた。
立ち去りがたく思いながらも、二人はベッドへと戻り眠りに就いた。
翌朝早く、子犬がしきりにキューキュー鳴いた。
いつもとは違う様子にアヤとミチは飛び起き、チビたちのもとへと駆けつけた。
子犬は一生懸命チビのおっぱいを引っ張りながら鳴いていた。
その横ではクロが頭を下げ、静かに座っている。
「どうしたの? チビ」
と声をかけても、チビは眠ったままである。
ミチが恐る恐るチビの体に手を伸ばすと、もうすでにチビの体は冷たく硬くなっていた。
「やっぱり昨日のがお別れだったんだね。チビにはもう分かっていたんだよ。」
昨夜、すでにチビの死を予感し、最期の時を一緒に過ごした二人は、案外すんなりとチビの死を受け入れる事が出来た。
もう二人ともゴンの死の時のように恐ろしさに立ち尽くすのみではない。
二人ともチビの愛を全身で受け止め、大きく成長していた。
チビの傍らに屈み込むと、アヤはそっと手のひらでチビの頭を撫でてやった。
子犬には、チビが死んでしまったという事など分からない。
ただ、おっぱいが出て来ないので悲しく、それで鳴いている。
チビは、気が狂わんばかりに欲した可愛い子犬を胸に、死んでいった。
その顔は微笑んでいるようでもあった。
終わり
子育ては体力勝負!こむぎ同様、 物語中の子犬もクロの愛に包まれて元気に成長しました。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
0同じカテゴリの記事
-
前の記事

秋田犬 夏の一日の過ごし方③(早朝の散歩タイム編) 2023.08.22
-
次の記事

秋田犬 夏の一日の過ごし方④(散歩後クールダウンタイム編) 2023.08.30