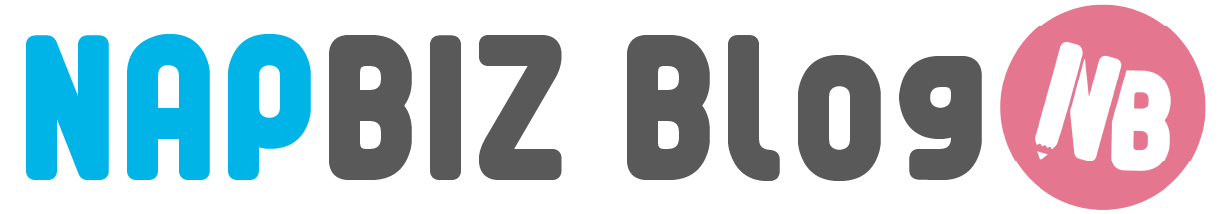ネコクイを追いかけろ! 第1話
「ネコクイを追いかけろ!」は、瀬戸内海に浮かぶ小さな島で夏休みを過ごすことになった少年の成長物語です。
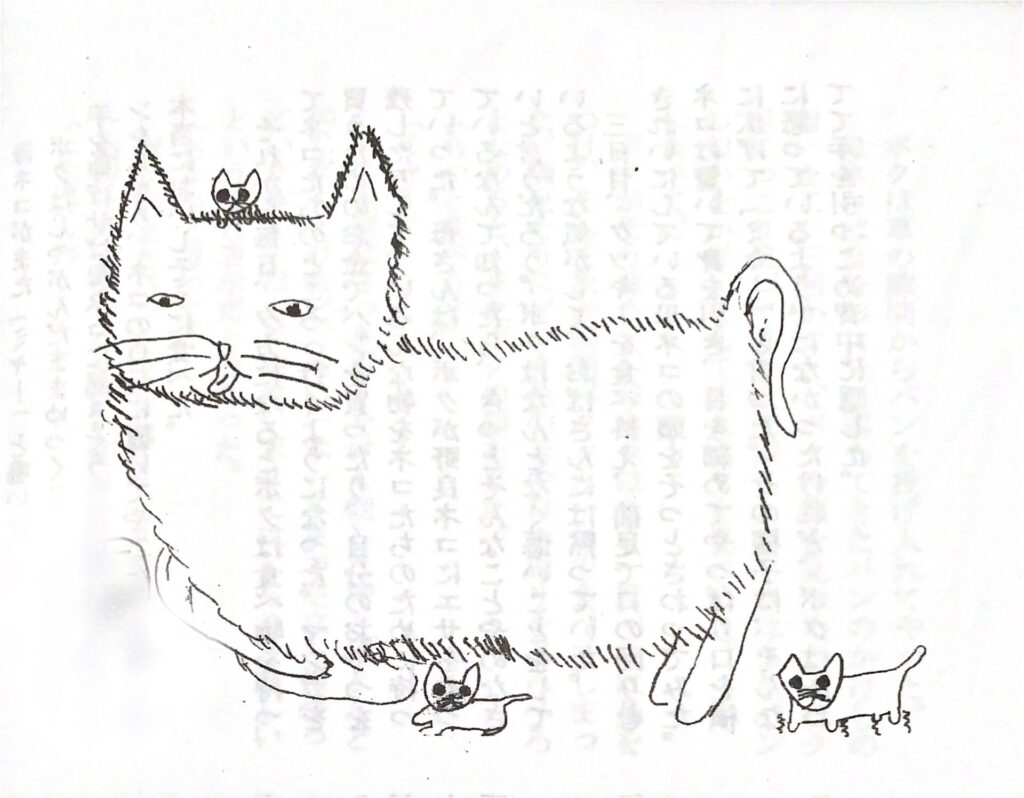
こんにちは。
秋田犬と暮らして23年、2頭の秋田犬を天国に見送り、現在2頭の秋田犬、虎毛の『ぱたこ』と赤毛の『こむぎ』との日々を楽しんでいるぱたこ母です。
今回も最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
【 第1話 】
「こうすけー、こっち、こっち!」
ボクがフェリーから降りると同時に、おばさんが大きく手を振った。
「どうやった、船の旅は? 酔わへんかった?」
「うん。」
「元気ないなー、疲れたんか?」
「ううん。」
「海がきれいじゃったろう、小さな島がいっぱいあって。
荷物、おばちゃんが持ってやろうか?」
「大丈夫です。」
おばさんは、ボクがここに来たくて来たんじゃないことをよく知っている。
ふだんは口数が少ないのに、ボクの機嫌をとろうと、言葉を選びながら次々と話しかけてくる。
「おっちゃんはな、仕事じゃけぇ、迎えに来れんかったけど、夜は早う帰って来る言うとったけぇ。」
次から次へとたたみかけるように話しかけてくるおばさんに対し、ボクは、自分が今ここにいることが大変不本意であるということを強調するために、「うん」としか答えなかった。
見ず知らずの土地にたった一人で降り立って、ほんの少し緊張していることに気付かれないためのポーズでもあった。
この夏、父さんのベトナムへの単身赴任が急きょ決まり、向こうでの生活を始めるにあたって、身の回りの細々した物を揃えるため、夏休みの間だけ母さんも一緒にベトナムへと旅立った。
その間、ボクはこの小さな島に住む、父さんのお姉さん夫婦の家に預けられることになったのだ。
都会育ちのボクに、自然の中で逞しくなってほしいという両親の魂胆が見え見えの計画だった。
父さんは何かにつけ、「父さんの島ではなぁ」と言うのが口癖だった。
ボクはそういう親の思いにほとほとうんざりしていた。
悔しい時に涙ぐんでしまうとか、外でサッカーをするよりも家の中で本を読むほうが好きだとかいうことのどこがいけないのだろう。
ゲームも取り上げられ、こんな海と山と畑しかない小さな島で、どうやって一ヵ月も過ごせというんだろう。
せっかくの夏休みだというのに、考えただけで体中の力が抜けてしまう。
おばさんには大学生の息子が一人いるが、大阪で下宿している。
だから、この家はおじさんとおばさんの二人暮らしだ。
五年前まではおじいちゃんも一緒に暮らしていたのだが、死んでしまった。
お葬式の時にボクはこの島に初めて来た。
ここに来るのはその時以来だ。

あの時はほんの六歳の子どもだった。
見るものすべてが真新しくて新鮮で、ボクの気持ちをワクワクさせた。
けれど、今のボクはもう十一歳。
ゲームとマンガとパソコンなしでは時間が過ぎていかない。
それなのに、ボクがこの島に持ってくるのを許されたものといったら、学校の課題図書と宿題の山と、たった1冊のマンガだけ。
この島には不釣合いな、クリーム色の壁に緑の屋根という洋風な造りのおばさんの家に着き、冷たい麦茶を一杯もらい、おじいちゃんの仏壇に手を合わせた。
写真の中のおじいちゃんは父さんに似ていた。
ボクも父さんに似ているとよく言われるので、年取って死ぬ前になったらあんな顔になるんだろうか、とぼんやり思った。
「そうだ、こうすけ。この前、裏の物置整理してたら面白いものが出てきたんだよ。見てみる?」
そう言いながらおばさんが仏壇の下の引き出しから出したのは、古ぼけたアルバムだった。
「こうすけのお父ちゃんの子どもの頃のアルバム。私も写ってるんじゃけどね。」
とおばさんは少し恥ずかしそうに笑った。
手渡されたアルバムをめくると、おばさんが横から覗き込みながら一枚ずつ説明してくれた。
「ほら、この若い女の人がおばあちゃん。抱かれてる赤ちゃんが、こうすけのお父ちゃん。」
「ほら、こっちに立ってるのが私で、隣で三輪車に乗ってるのがお父ちゃん。
こうすけの小さい時にそっくりじゃねぇ。」
懐かしそうに見入るおばさんとは対照的に、ボクは何の感情もなく、その白黒の写真たちを眺めた。
ページをめくっていくと、よれよれになった写真が一枚貼りつけられずにはさまっていた。
「あらっ、こんなところにすごい古い写真がまぎれこんで。これはおじいちゃんじゃねぇ。」
おばさんは写真を手に取り、裏返しながら言った。
『源太 十一歳』と書いてある。
「今のこうすけと同じ年じゃねぇ。よう似てる。」
日に焼けたように赤茶けたその写真には、海を背に、三人の坊主頭の少年たちが写っていた。
ボクの目から見ても、写真の中のおじいちゃんはボクに似ていて、タイムスリップしたような不思議な気分になった。
「こうすけ、今晩何食べたい? おばちゃん、料理得意じゃけぇ、なんでも作ってやるよ。」
おばさんはアルバムの最後のページをめくりながら言った。
「何でもいい。」
ボクはぶっきらぼうに答えた。
その言葉の突き放すような冷たい響きに自分でも驚き、慌てておばさんの目を気付かれないように盗み見た。
おばさんはにこやかな顔のまま、仏壇の中のろうそくの火を手であおぎ消している。
よかった。
おばさんを傷つけるつもりなんてこれっぽっちもない。
おばさんにふて腐れた態度をとったってしょうがないことも分かっている。
けれど、ボクは自分のどうしようもなく腐った気分を持て余していた。
「買い物ついでに散歩でもしようか!
こうすけ、この辺りのことなーんも知らんじゃろ。」
ボクはおばさんに強引に外に連れ出された。
庭とも畑ともとれる曖昧なスペースは細い川を挟んで車道に面している。

おばさんに付いて隣の家のひまわり畑を抜けると橋があり、その橋を渡るとすぐにスーパーは見えた。
「この道をな、左に行くとスーパー、右に行くと図書館やら公民館があるんよ。」
スーパーはすぐ近くに見えたのに、照りつける太陽のもと歩いてみると、全身汗びっしょりになった。
スーパーに着くまでの間、川には三本もの細い橋のようなものがかかっていた。
そのうちの一本はコンクリートで固められた割合しっかりしたものだったけれど、少し幅広の平均台といった感じで、手すりは無かった。
慌ててつまづいて転びでもすれば、そのまま川にドボーンだ。
水は少ししか流れていないから溺れる心配はないけれど、川底まで二メートルはあるので、すり傷か、或いはもっと酷いことになる可能性もありそうだった。
けれど、今まで見たこともない橋にボクは興味をそそられ、少し興奮した。
その場で渡ってみたい気もしたけれど、こんな島になどこれっぽちも感心がないという態度を貫かなければならないという変な信念から、おばさんに気付かれないように知らんぷりをして通り過ぎた。
あとの二本はもっと驚くべきものだ。
ボクの持つ橋というものに対する概念を根底からくつがえすような代物だった。
細い木の板が渡してあるだけの橋なのだ。
それこそ本当に平均台のようで、幅も五十センチほどしかなかった。
長さはほんの五メートルほどだけれど、その橋はたとえ頼まれても渡るのはごめんだと思った。
正直、怖かった。
「おばちゃんは夕飯の材料見てくるけぇ、こうすけはマンガでも見てな。」
スーパーの中に入ってすぐ左手にある本屋の前で、おばさんはボクに千円くれた。
次回に続きます。
↓↓↓
こうすけに必要なのはゲームとマンガとパソコンですが、ぱたこにとって無くてはならない物、それはモチモチボールとダンベルです。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
0同じカテゴリの記事
-
前の記事

秋田犬 夏の一日の過ごし方④(散歩後クールダウンタイム編) 2023.08.30
-
次の記事

ぱたこむ劇場(15)扇風機まで0距離💦怖いもの知らずな秋田犬ぱたこ 2023.09.08