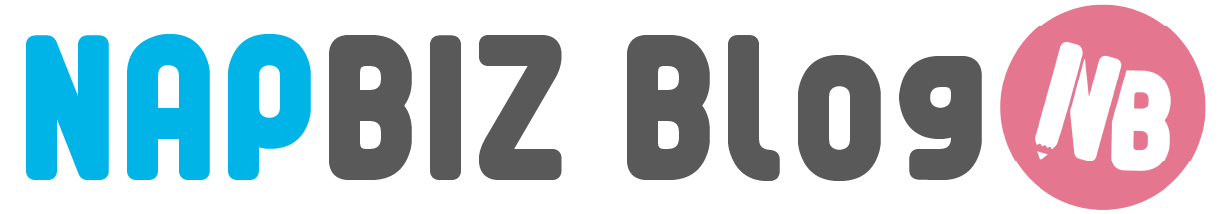ネコクイを追いかけろ! 第3話
「ネコクイを追いかけろ!」は、瀬戸内海に浮かぶ小さな島で夏休みを過ごすことになった少年の成長物語です。
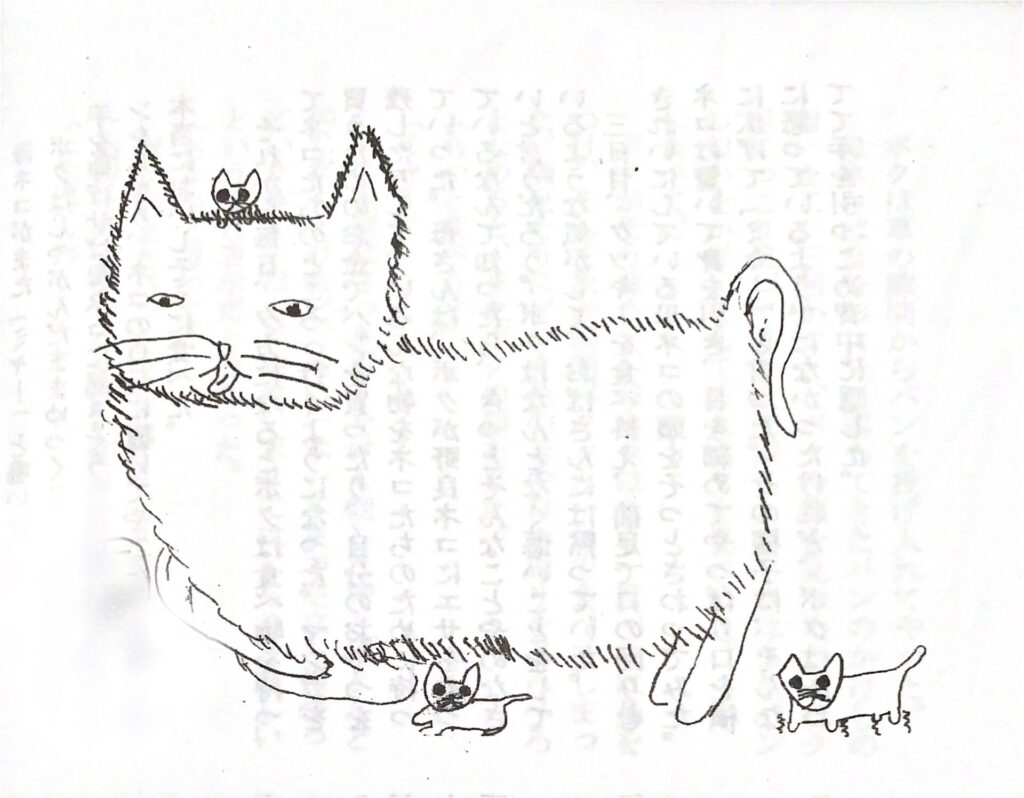
こんにちは。
秋田犬と暮らして23年、2頭の秋田犬を天国に見送り、現在2頭の秋田犬、虎毛の『ぱたこ』と赤毛の『こむぎ』との日々を楽しんでいるぱたこ母です。
今回も最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
↓↓↓第2話がまだの方はこちらからどうぞ
↓↓↓第1話はこちらからどうぞ
【 第3話 】
「パン、食べる?」
小さな声で優しくそう言ってみたけれど、ネコが答えるはずもない。
母ネコはいぶかしげにじっとボクを見つめるだけだ。
ボクは鉄棒をくぐり、ネコたちになるべく刺激を与えないように、ゆっくりと前に一歩踏み出した。
「ミャー」
と母ネコが一声、口を横に広げてボクをけん制した。
「大丈夫だよ。ほら、パン。」
ボクは草の隙間からパンを投げ入れてやった。
母ネコは自分の口元に落ちてきたパンのかけらの匂いを二、三回かぐと、ボクの顔を見つめた。ボクがにっこり笑って首を縦に振ると、ネコはまたパンの匂いをかぎ、そしてまたボクを見つめた。
「食べて。」
ボクがそう言うと、母ネコはもう一度パンに鼻をつけ、そして次の瞬間パクッと一口で食べてしまった。
満足そうにピンク色の舌で口の周りをぺろぺろとなめると、またボクの顔を見た。
「もっと食べる?」
「ミャー」
その表情はさっきボクをけん制した時とほとんど同じだったけれど、毛の一本一本まで逆立ち強張っていた体からは力が抜け、
ボクには「もっと欲しい」という意思表示だと分かった。
「ちょっと待って。」
ボクがまたパンを少しちぎり、さっきと同じように投げてやると、今度は一度匂いをかいだだけですぐに食べた。
よく見ると、左の方から回り込めば、ネコたちのところまで草の生えていない通路があることにボクは気がついた。
もう一かけら投げ入れてから、ボクはネコたちを驚かせないように、ゆっくりと左側にまわった。
ボクの全身が見えると、母ネコはまた口を横に広げた。
「ミャー」
ボクは母ネコを安心させるために、少し離れた位置でしゃがみ、また一かけら投げてやった。
ネコたちは木の根元に生えている背の低い草をクッションにしていた。

母ネコのお腹に抱えられた子ネコは三匹、すでに目は開いていて、きれいな青色の瞳でボクをじっと見ている。
よく見ると、母ネコも子ネコたちも特にやせているという感じはなく、毛なみもつやつやと良かった。
食べ物はなんらかの方法で手に入れているのだろう。
子ネコたちは三匹とも大きさが違った。
毛の色は、一番大きいのと小さいのが母ネコと同じオレンジ、そして残りの一匹はクリーム色だった。
母ネコがまた「ミャー」と鳴いた。
ボクはしゃがんだままゆっくりと一歩前に出た。
手を伸ばせば母ネコに届きそうな位置だ。
ボクがパンをちぎって口元に置いてやると、母ネコは本当においしそうに食べた。
それから毎日、夕方になるとボクは食べ物を持ってネコたちのところへ行くようになった。
マンガを買うためのお金でパンを買ったり、自分のおやつを残したりして、いろんな物をネコたちのために持っていった。
ボクが野良ネコにエサをやっているなんて知ったら、きっと母さんは「そんなことやめなさい」と言うだろう。
ボクはなんとなく悪いことをしているような気がして、おばさんには黙っていた。
三日目、クッキーを食べ終え、前足で口の回りをきれいにしている母ネコの頭をそっとさわってみた。
ネコは驚いて身を引き、目を細めてやっぱり口を横に広げて「ミャー」と言った。
その様子は、そんなに怒っているようではなかったけれど、ボクはあわてて手を引っこめて背中に隠した。
「ミャー」
「ごめん。」
「ミャー」
「だから、ごめんって。」
「ミャー」
ネコはのっそりと立ち上がると、子ネコたちはそのままに、ボクの足元までゆっくりと歩いてきて、その柔らかい体をこすりつけてきた。
ボクの足に体をすりつけながら背中のほうへ回るその姿は、ボクがまだクッキーを持っていると勘違いしてねだっているようだった。
ボクは後ろに組んでいる手をほどき、両手を母ネコの鼻先に開いて見せた。
「もうないよ。また明日持ってくるからね。」
ネコはボクの手をまん丸の瞳で見つめると、今度は目を細めてぺロッとなめた。
ざらざらしていて暖かかった。
子ネコたちが足を引きずるようにして母ネコを追いかけて来たので、ボクはネコの体を軽く押しやり、子ネコたちのもとへ戻るよううながした。
子ネコたちは日に日に大きくなり、一週間もすると歩きまわるようになった。
母ネコが立ち上がっても、おっぱいに吸い付いたままいつも引きずられていくのは一番体の大きなオレンジネコだった。
一番元気が良いのはチビのオレンジで、母ネコや兄弟たちにいつもじゃれついていた。
クリームネコはマイペースで、満腹になると地面につきそうなくらいふくらんだお腹を揺らしながら、ねこじゃらしの間を歩きまわっていた。
子ネコたちはボクが食べ物を持ってくるとわかっていて、顔を見るとミーミー大騒ぎするようになっていた。
ある日の朝、ボクはいいことを思いついた。
お昼を外で食べたいからと、おにぎりを作ることを許してもらう作戦だ。
しゃけ入りのおにぎりを一つ余分に持っていってもおばさんは怪しまないだろう。
おにぎりを作っていると、おばさんが台所に入ってきた。
「まあ、大きなおにぎりじゃねぇ。こうすけ、こんなに食べられるの?」
「うん。」
ボクは手を休めずに、おばさんの顔を見ないように言った。
「お友達とでも食べるん?」
「別に。」
おばさんとの話が長引いてぼろを出してしまわないように、ボクはつっけんどんに答えた。
「そうか、お友達できたんじゃねぇ、よかったねぇ。」
「違うよ、そんなもんできてないよ!」
勝手に勘違いして喜んでいるおばさんに無性に腹がたち、ボクはつい怒鳴ってしまった。
怒鳴るつもりなんてなかったのに。
おばさんがしつこくするからいけないんだ。
「そう・・・。」
おばさんの声は沈んでいた。
お盆のお供えのキュウリの馬とナスの牛の飾りを手慣れた様子でさっと作ると、寂しげな後ろ姿をボクの目に残し、和室へと出て行った。
仏壇から聞こえる鐘の音がボクの胸に沁みた。
心が痛み、怒鳴るべきじゃなかったと、ボクはいつものように後悔した。
気を取り直し、特大のしゃけ入りおにぎりを四つ作ることに成功したボクは、昼少し前にネコたちの喜ぶ姿を想像しながら公園へと向かった。

図書館への階段を上り、裏手の公園へと行こうとしたその時、大きな話し声が聞こえてきた。
「誰かいるのかよ。」
ネコたちの喜ぶ顔を楽しみに、せっかくおにぎりを作って持ってきたのに。
ボクは舌うちしながら、そっと公園を覗き込んだ。
けれど、声の主の姿はそこにはなかった。
ほっと胸をなでおろし、一歩ずつ辺りを見回しながらネコたちのもとへ向かう途中も、話し声は続いていた。
「だからそうじゃないって。ジャンプしながらぶっとばせって。」
「だから、ジャンプしながら・・・、こうだろ。」
「違う、違う、おせーんだよ。」
声は公民館との間の地底の道から聞こえてきた。
たぶん、ボクと同じくらいの年の男の子たちがゲームでもやっているのだろう。
けれど、その声はなんだか不自然だった。
話しているというよりも、誰かに自分たちがここにいるということをアピールするために、わざと大声をだしているという感じだった。
まさかボクに対して?
よそ者のボクがここに出入りしていることに感付いて、牽制するためにやっているのだろうか?
↓↓↓第4話はこちらからどうぞ
公園コース散歩では、こむぎがとてもはりきります♪
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
↓↓↓第4話はこちらからどうぞ
0同じカテゴリの記事
-
前の記事

ぱたこむ劇場(16) 姉が遊んでいた穴を横取りし、バチが当たって転ぶ秋田犬こむぎ 2023.09.23
-
次の記事

ぱたこむ劇場(17) 新しい宝物おしゃぶりパンダを手に入れた可愛い秋田犬ぱたこ 2023.10.14