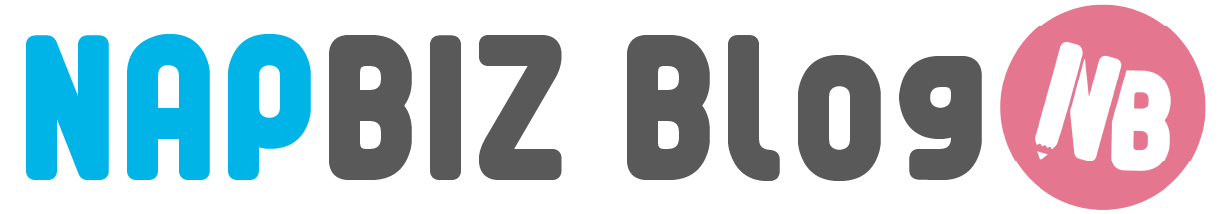煙突富士の見える坂 第6話(最終話)
「煙突富士の見える坂」は、中学受験を控えて憂鬱な気分の少年とちょっと不思議なおじいさんとの交流物語です。
こんにちは。
秋田犬と暮らして24年、2頭の秋田犬を天国に見送り、現在2頭の秋田犬、虎毛の『ぱたこ』と赤毛の『こむぎ』との日々を楽しんでいるぱたこ母です。
今回も最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
第5話がまだの方はこちらからどうぞ
第1話はこちらからどうぞ
【第6話】
「おじいさんには故郷の雪国なんて場所はないし、
そこに連れて行ってくれる息子なんてのもいないの。
確かに五年前までは息子がいたんだけど、
事故であっけなく死んでしまってね・・・。
おじいさんは随分ショックを受けて、
その頃から少しずつおかしくなってきちゃったのよ。」
おばさんの話など聞こえないかのように、おじいさんは夢見るような表情でじっと富士を見つめている。
「そうなんですか。」
ボクはおじいさんの悲しみを思うと、ただそれだけしか言えなかった。
「雪国っていうのは、たぶん兵隊の時に行っていた所だと思うわ。
おじいさんの人生の中で、戦争もとても大きな意味を持っていたと思うから。」
戦争と息子さんの死。
この二つの辛い出来事が今のおじいさんを作り出しているのかと思うと、あまりに悲し過ぎた。
「いつか息子が故郷に連れて行ってくれる。」
そうとでも思わなければ、やり切れない。
そんなおじいさんの思いが、ひしひしと伝わって来るような気がした。
「おじいさん、
早く息子さんが連れて行ってくれるといいね・・・。」
ボクは精一杯、明るく自然な感じを装ってそう言い、
おじいさんの膝の上に写真を返した。
自分を好きになるために勉強する。
おじいさんの言ったその言葉を胸に、
あの日からボクは少しずつ勉強に身が入るようになっていた。
八月も半ばになり、外は蒸しかえるような暑さのようだけれど、
ボクは暑さとは無縁の生活を送っていた。
夏休みに入ってからというもの、一日中クーラーのきいた部屋の中で机にむかっている。
この日は毎年恒例の引瀬川の灯籠流しがあるため、
いつもより早めの夕飯を済ませ、母さんは出かけてしまった。
「けんちゃんも一緒に行かない?
川を流れる灯籠、とってもきれいよ。」
母さんに誘われたけれど、
「まだ今日の分、勉強終わってないから。」
と断った。
母さんなんかと行ったって楽しくない。
小野とだったらな・・・。
灯籠流し、最後に行ったのはいつだったか。
楽しかったな。
ボクは全然勉強に集中できずにいた。
小野に電話をかけて誘ってみようかとも思ったけれど止めた。
今さら小野に会ったってしょうがない。
共通の話題なんて何もないんだから。
ゲームの話なんかされたら、自分が苦しくなるだけだ。
灯籠流し。
お盆に帰ってきた死者の霊を送るための灯籠。
おじいさんの息子さんも帰ってきたのだろうか?
そういえば、おじいさんはどうしているだろう?
夏休みに入ってから一度も会っていない。
この暑さの中でも、やっぱり毎日あの場所に座っているのだろうか。
おじいさんの弱々しい姿を思い浮かべると、ボクは急に胸騒ぎを覚えた。
おじいさんに会わなければ。
今、おじいさんに会っておかなければいけない。
灯籠流しという不思議な響きをもった言葉が、ボクをひどく不安にさせた。
はっきりした根拠もない強い思いに突き動かされ、ボクは家を飛び出した。
あせるボクの頭の中で、一つの思いが強く響く。
(おじいさんの息子さんの霊はきっと帰ってきている。)
マンションの前の大きな交差点をかけ抜け、古ぼけたアパートのブロック塀の前にボクは立った。
おじいさんはいない。
いるわけない。
もう夜の八時過ぎなのだから。
いなくて当然なのに、ボクの中を冷たい血がかけ抜けた。
そこにあるはずなのに、煙突富士も姿を隠している。
いつもそこにあるものが、無い不安。
おじいさんに会わなければ。
今、会って伝えなければ。
ボクも自分を好きになるって。
ボクは坂道をかけ下り、引瀬川をゆっくり流れる灯籠の淡い灯火を見つめた。

川面いっぱいに流れている灯籠。
たくさんの灯籠のうちの一つが、何かに引っかかってバランスを崩した。
中のろうそくが倒れて紙に燃え移り、その灯籠は強い炎を放ち、一瞬のうちに燃え尽きてしまった。
「おじいさん・・・。」
ボクはとてつもなく不安になった。
後ろからふいに肩をたたかれ、
ボクはおじいさんかと期待をこめて振り向いた。
が、母さんだった。
「ごめん、母さん!」
ボクはにこやかに笑う母さんのもとから走り去った。
おじいさんを探さなければ。
どんどん多くなってくる人の波をかきわけ、ボクは走った。
川沿いには露店が並び、みんなお祭気分だ。
そんな中でボク一人が必死だった。
何も考えられず、ただただおじいさんを探して走った。
橋にさしかかった所で息が続かなくなり、ボクは欄干にもたれかかって呼吸を整えた。
数えきれないほどの灯籠は幻想的な灯りをともし、どこまでも静かに流れて行く。
おじいさんはどこにいるんだろう。
どうしても今会いたかった。
今会わなければ、もう会えないような気がしてならなかった。
明日の朝まで待つなんてことは考えられなかった。
その時だった。
「待ってくれ。」
と弱々しく叫ぶ聞き覚えのある声がかすかに聞こえたのは。
ボクは慌てて周りを見回した。
「待ってくれ・・・、
待ってくれ・・・、」
と、声は遠ざかりながらも、なお聞えてくる。
声のする方に吸い寄せられるように人混みをかき分けて行くと、
見慣れた横顔が視界に入った。
おじいさんだ。
「おじいさん!」
ボクはありったけの声で叫んだ。
おじいさんはボクの声に気づき、
こっちを向いてきょろきょろすると、ボクを見つけてにっこり笑った。
ような気がした。
けれど、またすぐに前を向くと、
「待ってくれ!」
と言いながら、人混みにまぎれてしまった。
ボクは人の波の中を無理やりおじいさんの方に進み、
やっとの思いでおじいさんの腕をつかんだ。
「おじいさん!」
「放してくれ!
やっと息子に会えたんだ。
息子のところに行かせてくれ!」
おじいさんは振り向きもせずに、
弱々しい体のどこからそんな力がでるのか、ボクの手を思いきり振り払った。
「おじいさん、息子さんに会えたの?」
ボクは人混みの中、必死でおじいさんの後を追いかけながら聞いた。
「息子さん、どこにいるの?」
「そこじゃ、そこ。」
おじいさんはそう言いながら川の中を指さすと、遊歩道から外れ、
土手を滑るようにして川へと飛び込んでしまった。
「おじいさん!」
ボクは悲鳴にも似た声で叫んだ。
おじいさんが指さした先には、
燃えて骨組みだけになってしまったさっきの灯籠があった。
春になり、ボクは希望していた中学の真新しい制服の袖に腕を通した。
あれだけ悩んでいたのに、今は清々しい気持ちでいっぱいだ。
一番に合格を知らせたかったぶどう色の瞳のおじいさんは、もういない。
灯籠流しの夜に救急車で運ばれて以来、いつもの場所にまだ戻ってきていない。
老人ホームに入ったとか、
死んでしまったとか、
いろいろな噂が流れている。
けれど、ボクは煙突富士に向かって自転車で坂道をかけ下りながら、
胸いっぱいに気持ちの良い空気を吸いこみ、思う。
おじいさんは望み通り、息子さんと故郷に帰ったんだろうと。

終わり
【夏の休息】暑い夏の日は秋田犬ぱたこと一緒にお昼寝
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
これまでの作品はこちらからどうぞ
広告
同じカテゴリの記事
-
前の記事

秋田犬ぱたこむ劇場(31)遅く起きた朝はペロペロ部隊に挟まれてゆっくり食事ができない秋田犬のいる生活 2024.04.13
-
次の記事

眠れない夜とさようなら! 睡眠の質を上げるために必要な3つのポイント(第1回) 2024.04.24